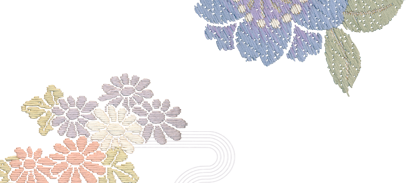一歩引いた大人の使いやすい色
昨年の暮れ、京都の三浦清商店さんに伺い、帯揚げを染めて頂きました。
色使いでいつも素晴らしいと尊敬するのは清野恵理子さんです。
彼女の本はどんな時に眺めても飽きることがなく、ちょっと休憩してお茶を飲むときにいつも手に取って、色の世界にうっとりしています。
その清野さんが撮影でご使用になる帯揚げは京都の三浦清商店さんで染めたものと伺っていたので、いつかは・・・と。
そんな思いを抱いていた頃から少しだけ長いときが経ち、やっとお願いすることが出来たのが、昨年の暮れ。
どんな色を染めたいのかをご主人にお伝えして、沢山の色見本を見せて頂きました。
その時「雪乃先生ですよね、いつもご活躍を拝見しております」とお声をかけて頂きました。
私を知ってくださるなんてと驚きましたが、とても嬉しかったです。
実は昨年は試練の年でもありました。
ずっとやりたかったNHKの番組を担当させていただく一方で、頼まれた着物業界の講演などでは、会場の皆さんが私を知らず、責任者の方にあなたは一体誰ですか?と言われることが何回かありました。
約束の時間に伺っても、講演はしなくていいからと言われたり・・・。
とてもショックで、私は今まで何の仕事をしてきたのだろう?と自問自答する日が続きました。
ただ、その時に受けた恥ずかしさや自信喪失の経験は、いったん歩みを止めまわりを見渡す良い機会となり、これからどう仕事と向き合っていくのかが明確に見えてきた大事な転機になりました。
学びとはこういう所にあるのだと、のちに深く感謝する気持ちに。
ですので、三浦商店さんが私の仕事を知っていて下さったことは、とても嬉しかったです。
帯揚げで良く使うのは、灰白色という色です。
わずかに灰色が入った白です。
濃い色の帯をするときは白っぽい帯揚げが抜け感があり良いのですが、その白さが帯を引き立たせる場合と逆に潰してしまう時もあり、かなり気を使います。
PCでははっきりわかりづらいかと思いますが、赤みをおびた灰白色は、グレートーンの中に優しさや柔らかさが入ります。
青みをおびた灰白色はクールに透き通った静かさを表現しています。
ニュートラルな灰白色は何にでも合わせやすい色です。
濃い灰色は鈍色
平安時代では出家の色とも言われています。また儀式のときに高貴の僧が着る法衣の色でもあります。
更紗などの古裂を使った帯や、祖母の古い帯などは現代の色では調和がとれないので、鈍色は重宝します。
気難しい色ですが一度理解すると手放せなくなります。
えび茶は青み系。鳶色は黄み系、どちらも赤みのある茶色。
大人の色ですね。
こういう色目が使いこなせるようになると、きものはとても楽しくなります。
ビビットな現代色は表面的な色で、深みがありません。
大人の女性は少し控えめであっても芯の通った色を使って欲しいと思います。
また顔周りにあまり鈍い色を持ってこれないので、帯周りはこういう色で落ち着きを持たせるとバランスが良いです。
40代以降からの色です。
色は、合わせるものによって微妙に変化を持つことが出来るニュアンスカラーであること。
それは何よりも染色職人の目に100%頼らなければならない部分です。
もし気になる色やご質問などがございましたらメールを頂戴すれば少しでしたら対応できるかと思います。
白生地は清野恵理子さんと同じ一番重めの縮緬を使いました。
上質のちりめんは、しわにになりにくく、結んだときにふっくらと仕上がります。
色の仕事は地味ではありますが、女性を引き立たせる大事な仕事。
2017年度の新規クラスも5月開講となります。
ぜひご一緒に色の勉強を始めてみませんか?
おまちしております。
https://www.traditional-colorist.org/メニュー/スクール-レッスン/